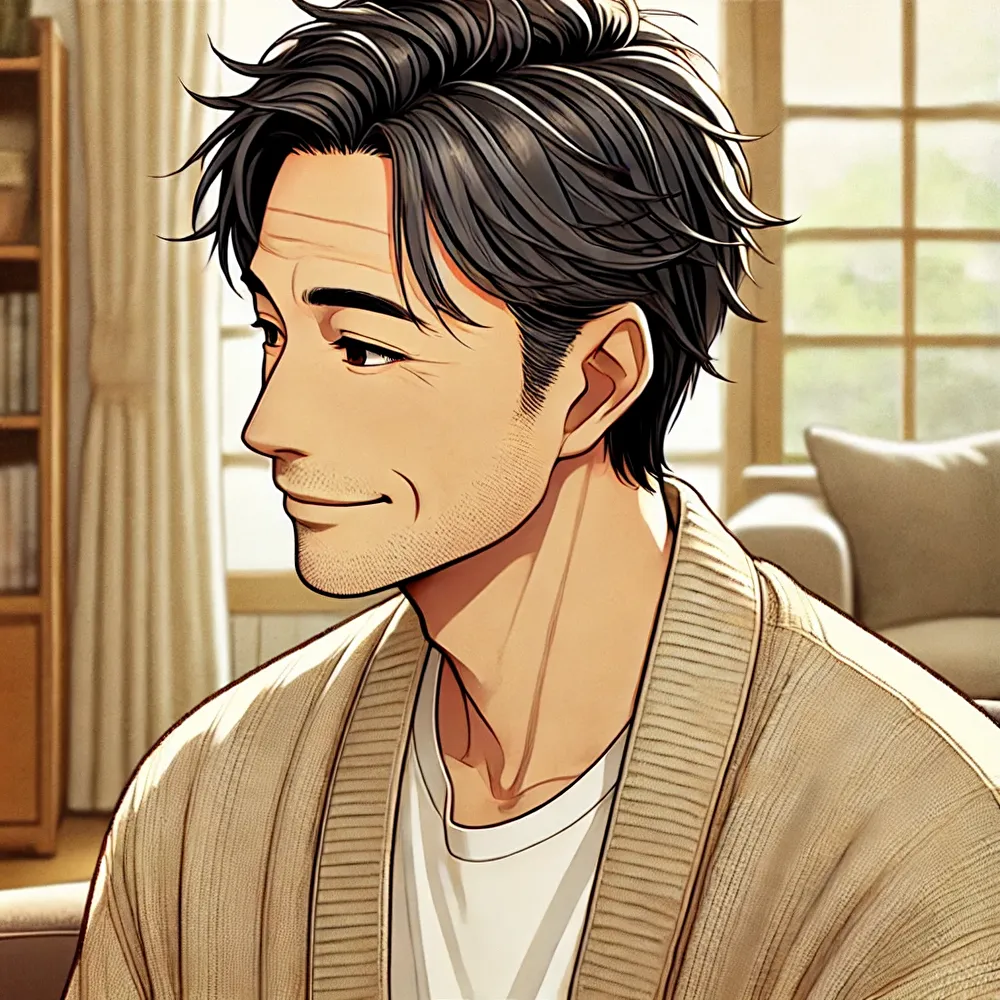*当ページにはプロモーションが含まれています。
約12分で読めます床の美しさを長持ちさせる「ポラスのフロアコーティング」が気になる方へようこそ。
新築住宅を検討中の方にとって、床面のメンテナンスや費用対効果は大きな悩みのタネですよね。
せっかくの新築なのに、フローリングが傷だらけになったり、ワックスを何度も塗り直す手間がかかったり…そんな不安は誰しも抱くと思います。
そこで注目されるのが、長期的に綺麗な床を維持し、かつ「将来の床張替え費用が浮くかもしれない」という便利な技術です。
まさにこの技術を代表するものが、ポラスグループが提供する床コートサービス。
しかし「本当に必要なのか?」という疑問も湧くでしょう。
実際に調べると、ガラス系やシリコン系、UVコーティングなど種類が多く、比較が難しいと感じるかもしれません。
しかも料金面では数万円から数十万円と幅があるため、「どの施工業者に依頼すべき?」と迷われる方も多いはず。
また、ポラス本体が推奨するサービスと、外部の施工業者を直接探す方法では、費用面にもばらつきがあります。
施工後の剥がれやムラ、保証内容の違いなど、知っておきたい要素も山ほど。
まさにこれらの疑問に、この記事でまとめてお答えします。
もしあなたが、しっかりと情報を集めて「後悔しない決断」をしたいなら、ぜひ最後までお付き合いください。
実は、複数社の見積もりを取り寄せて比較するだけで、同じような施工でもコストが大幅に変わることは多々あります。
「これから一社に決めようと思っていたけど、じっくり比較する時間がない…」とお悩みの方も安心してください。
今はタウンライフ家づくりなどの無料サービスで、一度に複数の施工や建築プランをチェックできます。
じつは私も同様のサービスを使うまでは、見積もりの取り方ひとつでこんなに差が出るのか…と驚かされました。
(※この後に詳細を述べますね)
高いお金を払って後悔するよりも、無料で比較検討したうえでベストな選択をするほうがずっとお得です。
さらに記事中では、床暖房との相性やお手入れ頻度、ペット対策など、実際の暮らしに直結する内容も取り上げます。
あなたの生活スタイルや予算に合った最良のコーティング方法を一緒に見つけていきましょう。
読み進めると、なぜ複数社の見積もりが大事なのか、そのメリットがはっきりと理解できるはずです。
そして最終的には、リセールバリュー(中古売却時の査定)にもプラスの影響が期待できる理由を詳しく解説します。
なお、本記事では専門的なデータだけでなく、実際に導入して良かった・失敗したなどの声も紹介。
徹底的に情報をまとめておりますので、読後には「自分の家庭にフロアコーティングは必要かどうか」をクリアに判断できるでしょう。
それでは、まずはポイントをサクッとお伝えしますね。
この先で、より具体的に施工内容やメリットを掘り下げていきます。
もし「新築を検討中だけど、もう少し詳しくプロの意見を聞きたい」という方は、タウンライフ家づくりで複数社の情報を一度に請求してみてください。
無料で使えて気軽ですし、余計な営業電話を減らせる工夫もされています。
- 床材下地の重要性とコーティングの種類がわかる
- 施工前後の安全性や耐久年数の具体例が理解できる
- 費用相場と業者比較のメリットを知れる
- ペットや子育て環境への適用ポイントが学べる
- 将来的な売却価値や保証制度までまとめて把握できる
Contents
- 1 ポラスのフロアコーティングを検討するポイント
- 2 ポラスのフロアコーティングが生む長期メリット
ポラスのフロアコーティングを検討するポイント
- 新築住宅での耐久年数と再施工費
- 各種塗料の安全基準とVOC値
- 施工前に行う床材下地の詳細チェック
- シリコン系とガラス系の硬度比較事例
- 施工後の生活感想とメンテナンス周期
- リセールバリューと査定価格への影響
新築住宅での耐久年数と再施工費

この章のポイント:
- コーティングの種類別・平均的な寿命と費用
- 再塗装が必要になる時期と費用対効果の考え方
- 耐久性を左右する施工当日の注意点
ポイント1.種類別の平均寿命とコストを解説
フロアコーティングには、シリコン系やウレタン系、ガラス系やUV硬化など多様な種類があります。
それぞれ密着度や硬度が異なるため、一般的には「ガラス系」や「UVコート系」は比較的長い耐久年数を誇り、10~30年程度も保つ事例が見られます。
一方、シリコン系は5~15年、ウレタン系は3~10年ほどとやや短めです。
もちろん床材や使用状況によって左右されるため、この数字はあくまで目安ですが、長い目で見れば「最初に高耐久タイプを施工したほうがコスパがいい」という意見が多いですね。
施工費は、種類によって大きく異なります。
たとえばガラスコーティングは20万円前後、UVコートは30万円以上かかることも珍しくありません。
「初期費用が高い」と感じる方もいるかもしれませんが、ワックスで定期的に塗り直す手間や床材の劣化による張替えのリスクを考えると、長期的にはお得になるケースが多々あります。
実際、フローリングの全面張替えは1回で100万円単位の出費も見込まれるため、「10年後や15年後の出費を抑えたい」という方にはフロアコーティングが役立つ可能性が高いでしょう。

「床を一度傷めてからリフォームする」より、はじめに保護しておく方が意外と節約になることが多いんです。
ポイント2.再施工のタイミングとメンテナンス費用
たとえ高耐久タイプを選んでも、経年とともに傷や汚れは蓄積します。
その場合、部分的な補修で済むこともあれば、再施工が必要なケースも。
例えばガラスコーティングの場合、10年以上経過してヘタりが目立つ部分があれば、部分再塗装が検討されます。
施工範囲を限定すれば費用を抑えやすいですが、一部だけ色合いが変わる可能性もあるため、施工業者やポラスの担当者としっかり話し合うことが大切です。
再施工費の目安は、フルでやり直す場合で初回費用の6~8割程度という話が多いです。
しかし、使用塗料や平米数によって見積額が変動するため、一概には言えません。
また、施工の下準備に床をクリーニングする作業が必要になると、追加費用がプラスされることも。
コーティングの上から重ね塗りできる塗料と、いったん古い塗膜を削らなければならない塗料では、下地処理にかかるコストが変わるので要チェックです。

でも長く住む家なら、先々まで考えておくと安心です。
ポイント3.施工当日の環境が耐久性を左右
実は、フロアコーティングがどれだけ長持ちするかは「施工当日の状態」に左右される要素も大きいです。
例えばホコリの除去や床材の湿度、温度管理が不十分だと、塗膜に小さな気泡が入りやすくなります。
これが経年劣化を早める原因になることもしばしば。
特に新築時に施工を依頼する場合、建築工程の進捗状況を確認しながらスケジュールを組む必要があります。
ポラスの場合でも引き渡し直前の施工になるケースが多いので、クロス貼り作業や設備取り付け工事などの粉塵が残っていないか、必ずチェックしてから着手しましょう。
また、入居後の家具の搬入が先になったりすると、せっかくの塗膜が傷つくこともあり得ますので、業者とよく連携を取ることが大切です。
こうしたポイントを押さえて施工すれば、耐久年数を最大限に引き延ばし、「家族みんなが気持ちよく使える床」を長期間維持することが可能になるでしょう。
主要なコーティング種類ごとの耐久年数の目安
| コーティング種類 | 耐久年数目安 | 備考 |
|---|---|---|
| ウレタン系コーティング | 5~10年 | 低価格帯で施工が容易ですが、耐久性は比較的短く、定期的な再施工が必要になることが多い。 |
| シリコン系コーティング | 10~15年 | 一般住宅で広く採用され、費用対効果が良いとされる。耐久性はウレタン系よりも優れている。 |
| ガラスコーティング | 20年以上 | 見た目の美しさと高い耐久性が特徴。再施工の頻度が低く、長期にわたって美観を維持できる。 |
| UV硬化コーティング | 20年以上 | 一部製品では30年持続の実績も報告されており、長期保証が付くケースもある。高性能を謳う製品が多い。 |
| ナノガラスコーティング | 約20年以上 | 最新技術を応用した製品。従来のガラスコーティングと同等またはそれ以上の耐汚性・耐摩耗性を実現している。 |
この表は、各種コーティングの耐用年数の目安を示すものであり、実際の耐久年数は施工環境や使用状況、製品ごとの仕様によって変動する可能性があります。
最新の情報や具体的な製品仕様は、各メーカーや施工業者の資料・保証内容をご確認ください。
ここまで読んで、「具体的なコストシミュレーションをもっと知りたい」と思った方は、一度複数の施工業者の見積もりを比べてみてはいかがでしょうか。
タウンライフ家づくりなどの無料サービスを活用すれば、希望するコーティング方法や予算感を同時に伝えられるので、後々比較が楽になりますよ。
各種塗料の安全基準とVOC値
この章のポイント:
- 日本国内のシックハウス対策と塗料の基準
- 小さな子どもやペットへの安全性
- 施工現場での換気と健康リスク
ポイント1.シックハウス対策と国内法規の実情
近年の住宅では、シックハウス症候群への対策が重要視されています。
フロアコーティング剤も例外ではなく、使用される塗料の成分がホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)をどの程度含むかがポイントとなります。
日本国内では「F☆☆☆☆(エフフォースター)」等級をはじめ、厳しい安全基準が定められており、多くの施工業者はそれに準拠した塗料を使っています。
ポラスの住宅で推奨される塗料も、基本的にはF☆☆☆☆等級や食品衛生法に適合した材料が中心です。
ただし塗料の臭気が多少なりとも発生する場合もあるため、施工時には数日間の換気を行うように指示されるケースがほとんど。
新築時ならまだ入居前なので問題ありませんが、住みながらの施工や小さな子ども・高齢者がいる家庭では、スケジュール管理を慎重に行いたいところです。
ポイント2.子どもとペットへの影響を最小化
床を舐めたり、ハイハイをする赤ちゃんがいるご家庭では、安全性は特に気になるでしょう。
実際、「コーティングして大丈夫なの?」と心配する声も珍しくありません。
しかし近年の高性能塗料は、乾燥後に有害成分がほぼ揮発しないものも多く、ペットが床を舐めても影響が少ない製品が増えています。
たとえばガラスコーティングの中には、食品衛生法の適合テストをクリアしており、「安心して使える」とPRしているものもあります。
加えて、塗膜が硬いほど爪や歯による傷がつきにくくなるという利点も。
これらの点から、ポラスの施主さんの中には「ペットを迎えるタイミングで施工してよかった」という事例がいくつも報告されているんです。

ポイント3.施工時の換気とリスクヘッジ
どんなに安全基準をクリアした塗料でも、施工直後は多少の揮発物質が発生します。
そのため、施工日と翌日はできる限り窓を開けたり、換気扇をフル稼働させるなどの対策が推奨されます。
特に夏場は高温多湿で揮発が遅れがちなので、追加で扇風機を使用したほうが効果的です。
また、初日の段階でどうしても臭いに敏感な方や小さな子ども、ペットがいる場合は、別の場所に一時的に避難する方法も検討しておくと安心です。
こうしたリスクヘッジを行うことで、健康面のデメリットを最小限に抑えられます。
施工業者とコミュニケーションをしっかり取り、「どのタイミングなら安全か」を確認してスケジュールを組むことが鍵と言えるでしょう。
主要なフロアコーティング用塗料別のVOC(揮発性有機化合物)値の目安
| 塗料種類 | VOC値目安(g/L以下) | 備考 |
|---|---|---|
| ウレタン系塗料 | 約300~500 g/L | 従来型のウレタン塗料はVOCが高め。低VOC製品も存在するが、一般的にはやや高い数値。 |
| シリコン系塗料 | 約100~200 g/L | 一般的なシリコン系塗料はウレタン系に比べて低VOC。環境配慮型として採用されることが多い。 |
| ガラス系コーティング | 約50~100 g/L | ガラス系は有機溶剤の使用量が少なく、VOC値が低いものが多い。環境・健康面で評価される。 |
| UV硬化塗料 | 約20~50 g/L | UV硬化塗料は溶剤使用量が最小限に抑えられており、VOC値が非常に低いのが特徴。 |
| ナノガラスコーティング | 約20~50 g/L | 最新技術を用いた製品はUV硬化と同様、低VOCを実現。耐久性と環境性能が高いとされる。 |
※注意:
- 数値はあくまで一般的な目安であり、製品ごとに異なる場合があります。
- 低VOC塗料の場合、乾燥時間や施工性が従来の高VOC塗料と異なる場合があるため、施工条件の確認が必要です。
- 最新の環境規制(例:日本の建築材料規制、EUのVOC規制など)に適合した製品かどうかも、メーカーの公表資料をもとに判断してください。
こうした安全面を踏まえたうえで、「ちゃんと低VOC塗料を使っている業者かどうか」は見極めたいところ。
複数の業者から事前に説明を受けておけば、費用だけでなく安全性比較も一度にできますので、タウンライフ家づくりなどを賢く活用してみてくださいね。
施工前に行う床材下地の詳細チェック

この章のポイント:
- フローリングの素材と元々の塗装状態を把握する
- 前処理の有無で仕上がりに差が出る理由
- 専門家の下地診断でトラブルを回避
ポイント1.フローリング素材の違いを確認
施工前に必ず確認したいのが、フローリングの素材です。
合板タイプの上に化粧シートを貼ったものから、突き板、無垢材まで幅広いバリエーションがあります。
また近年は、ワックスフリー仕様の床材も多く流通しており、新築住宅のポラス物件でも採用されるケースが増えています。
この素材の違いによって、コーティングの吸着力や仕上がりの質感、さらには必要な下地処理が変わるんです。
例えば無垢材は湿度の影響を受けやすいため、施工前後の温度管理をより慎重に行う必要があります。
一方、化粧シートタイプは「そもそもワックス不要」である程度の保護層があるため、コーティングしてもしなくても良いという意見を持つ専門家もいます。

逆に化粧シートタイプなら、薄いガラスコートをプラスするだけでグッとメンテナンスしやすくなるパターンがあります。
ポイント2.下地処理が仕上がりを左右する要因
実際のフロアコーティングでは、床材の表面を整える「下地処理」が欠かせません。
具体的には、掃除や脱脂作業、既存のワックスや汚れの除去などが含まれます。
これを怠ると、塗膜がムラになったり、早期に剥がれたりする可能性が高まるのです。
新品のフローリングでも、工事段階でついた微細な傷やホコリが残っている場合があります。
施工担当はそれを丁寧に拭き取り、必要に応じて軽い研磨を行ったうえで塗装しますが、短縮工程で進められた場合は後々トラブルになりがち。
だからこそ「この業者は下地処理をどれだけ重視しているか」は見積もり時点で確認したいポイントです。
また、下地処理が甘いまま塗装すると、床材内部の湿気が逃げ場を失い、経年で塗膜が浮いてくることも…。
「最初の状態が肝心」というのは、どんな仕上げ作業にも共通する真理でしょう。
ポイント3.専門家による下地診断の必要性
下地処理や床材の状態チェックは、素人目にはなかなか難しいもの。
とくに新築住宅でも、目視では分からないレベルの傷や施工不良が存在する可能性はゼロではありません。
そこで、信頼できる施工業者やポラスの担当者が「床材下地診断」を行い、問題点を洗い出したうえで最適なコーティング法を選択することが重要です。
もし複数の業者に見積もりを依頼するなら、「床材下地の診断を無料でやってくれるか」「どのくらいの精度で確認してくれるか」をチェックしておくといいでしょう。
実際、複数社に依頼すると「A社では問題なしと言われたが、B社では小さな欠陥を指摘された」というケースも起こります。
こうした差を把握できるのも、一括で複数見積もりを取る利点のひとつです。
想定外のトラブルを回避するためにも、下地処理や床材診断の大切さは覚えておきましょう。
「他社と比較してもやっぱりポラスの施工がいいのか?」と疑問に思う方は、ぜひタウンライフ家づくりで検討の幅を広げてみてくださいね。
シリコン系とガラス系の硬度比較事例

この章のポイント:
- 代表的コーティング2種の特徴と仕上がり
- 硬度や防汚性能の比較による選び方
- 生活スタイルに合わせた素材選定のヒント
ポイント1.それぞれの特徴と仕上がりイメージ
フロアコーティングの代表格ともいえる「シリコン系」と「ガラス系」。
シリコン系はやや光沢が強く、施工費も比較的安価な傾向がありますが、耐久年数は10年程度と中長期向き。
一方でガラス系は、光沢が控えめで自然な雰囲気が残るうえに、硬度も高いというメリットがあります。
「床にピカピカ感を求めたい」「費用は抑えつつ10年くらいもてばOK」という方にはシリコン系がマッチしやすいです。
反対に「落ち着いたツヤ感を維持したい」「20年以上長持ちしてほしい」という希望がある場合はガラス系が人気を集めています。

ガラス系なら床の色味をあまり変えずに保護できるから、インテリアのこだわりがある方にも評判いいです。
ポイント2.硬度と防汚性能の実際
硬度については「ガラス系>シリコン系」と言われることが多く、ガラス系は鉛筆硬度9H相当と非常に硬い塗膜を形成する製品もあります。
シリコン系はそこまでの硬度はありませんが、弾性があるため衝撃吸収に優れるという見方も。
つまり、何に重点を置くかで適切な選択が変わってくるわけです。
防汚性能に関しては、ガラス系もシリコン系も「汚れが染み込みにくい」「水拭きで簡単に落とせる」という共通点があります。
ただし、油汚れやペットの排泄物を放置した場合、ガラス系の方がシミになりにくいとの報告事例も多いです。
この辺りは施工業者のブログや口コミを参照し、具体例を確認すると信頼度が高まります。
ポイント3.どちらがライフスタイルに合うかを考慮
家族構成やライフスタイルによって、コーティングの選び方は変わるもの。
例えば小さい子どもがいるご家庭なら、ガラス系で床が固すぎると「転倒時の衝撃がやや強い」と感じるかもしれません。
また、家具を頻繁に動かす場合や床暖房を多用する場合は、ある程度の弾力があったほうが剥がれにくいことも。
ただしガラス系でも、最近は微妙に弾力を持たせた新素材が登場しているので、一概に「硬い=衝撃に弱い」とは言えなくなってきています。
結局は「どの製品を使うか」が重要。
比較検討に時間をかけるほど自分に合ったものが見つかりやすいので、複数社からカタログを取り寄せてみるのがおすすめです。
そこで、タウンライフ家づくりのようなサービスを活用すれば、大幅に調査時間を短縮できますよ。
施工後の生活感想とメンテナンス周期

この章のポイント:
- 使用者のリアルな体験談から見えるメリット
- 掃除方法とメンテナンス頻度の具体例
- 実際の生活シーンで気をつけたい注意点
ポイント1.実際に導入した人の声
実際にポラスの家でフロアコーティングを導入した方の多くは、「床掃除が楽になった」という感想を挙げています。
特に小さなお子さんがいる家庭や、ペットを飼っている家庭では、日々こぼれた飲食物やペットの足あとなどが床に付着しがち。
それでも、コーティングされていると軽い拭き掃除だけでスッと汚れが落ちると好評です。
一方で、「光沢が増して、最初は少し目がチカチカした」という声や「家具の移動で擦り傷がつかないわけではなかった」という意見も。
完全に傷がつかない魔法の塗装ではないため、ある程度の注意は必要です。
ただ、未施工の場合と比べると傷の深刻度が軽減され、修復可能なケースが増えるのも事実。
ポイント2.掃除方法と日常的なケア
コーティング施工済みの床は、水拭きだけで大半の汚れが落とせるため、ワックスがけの必要はほとんどありません。
掃除機をかける前にクイックルワイパーなどのドライシートでホコリを取っておくと、塗膜を傷つけにくくなります。
また、使う洗剤については中性洗剤を薄めたものやフロア専用クリーナーが推奨されることが多いです。
高圧スチームクリーナーなどを使う際は、塗膜にダメージを与える恐れもあるので、メーカー推奨の使用方法を確認しましょう。
ポラスの住宅向けコート剤なら、中性洗剤やアルコール除菌シート程度なら大丈夫なケースが多いですが、強力な溶剤系は避けるべき。
また、床材の継ぎ目に水が入り込まないよう注意すれば、基本的には長期間美しい状態を維持できます。
ポイント3.生活シーンで気をつけたいポイント
コーティング後の床は、表面がツルツルになる分、靴下やスリッパの素材によってはやや滑りやすく感じることがあります。
慣れるまでは気をつけて歩くようにしましょう。
また、重い家具を引きずると、塗膜に細かい傷が入る可能性が高いです。
家具の下にクッション材やフェルトを貼っておくと傷防止に効果的。

でもコーティングのおかげで深いダメージにはならず、部分補修で済んだので助かった経験がありますね。
このように、日常生活でのケア方法を把握しておけば、コーティングの恩恵を最大化できます。
自分の生活スタイルに合うかどうか、まだ迷う場合は「本当に必要かな」と思うポイントを整理しながら、ぜひ複数社へ相談を。
ここでもタウンライフ家づくりを活用して、一括で比較するのがおすすめです。
リセールバリューと査定価格への影響

この章のポイント:
- フロアコーティングが中古価格に及ぼすプラス効果
- 買い手が注目するポイントと印象づくり
- 査定士の視点から見た床の評価基準
ポイント1.中古住宅市場でのメリット
意外に知られていないのが、フロアコーティングが中古売却時にプラス評価を受けるケースです。
確かに工法や塗料の種類までは詳細に査定されない場合もありますが、「床の傷が少ない」「築年数のわりに綺麗」という印象がつくと、それだけで買い手の評価が上がります。
ポラスの家はもともと構造面で評価が高い傾向にありますが、床の状態が良好なら「内覧の第一印象が非常に良い」というメリットが。
「築10年なのにここまで綺麗なんだ!」と感じる買い手が増えれば、競合物件に比べて有利になる可能性大です。
したがって、結果として売却価格にも良い影響をもたらすことがあります。
ポイント2.内覧時に買い手が注目するポイント
実際に中古住宅の内覧を経験した人の多くは「キッチンや浴室といった水回り」「収納スペース」「床や壁の汚れ具合」などに注目すると回答しています。
特に床は広範囲で目に入るため、傷や汚れが目立つと「メンテナンスされていない家」という印象を与えがちです。
逆に、床が綺麗に保たれていれば「大切に使われてきた住まいなんだな」と好印象を持たれる確率がぐんと上がります。
現に、フロアコーティングをしていたオーナーさんの体験談を見ると、内覧初日に申し込みが入ったケースも珍しくありません。
その「第一印象づくり」をサポートするのがコーティングの力とも言えます。
ポイント3.査定士が評価する床状態の要素
不動産査定では「築年数」「場所」「面積」などの客観的要素がメインになりますが、「建物のコンディション」も加点要素の一つです。
具体的には、床材のへたりや大きな傷、汚れ、張替えの必要性などがチェックポイント。
フロアコーティングが施されており、床材が良い状態で残っているほど「張替え不要」と見なされ、マイナス評価を回避しやすいんです。

長期的な資産価値を考慮すれば、フロアコーティングは「単なる見た目のオシャレ」以上の意義を持つかもしれません。
特に数十年スパンで考えるなら、今のうちに施工しておくメリットは十分にあると言えるでしょう。
ポラスのフロアコーティングが生む長期メリット
- ペットと子育て世帯でのキズ対策
- 床暖房対応の材質選びと断熱性能
- 高温多湿地域でのコート効果の検証
- 施工保証制度とアフターサポート事例
- 他社業者比較で見る費用分布と割引情報
- ポラスのフロアコーティングを導入する利点
ペットと子育て世帯でのキズ対策

この章のポイント:
- ペットの爪や子どものおもちゃ等で発生する傷を防ぐ
- 家族全員が快適に暮らせる床の実現方法
- コーティングによる滑り防止機能の進化
ポイント1.ペットの爪と子どもの玩具が床に与える負荷
ペットと暮らすご家庭では、犬や猫の爪痕が気になりませんか。
特に犬の爪はフローリングにとって大敵であり、日々のランダムな傷が蓄積すると見た目がどんどん荒れてしまいます。
子どもがいる場合も、おもちゃの車を床に走らせたり、椅子を引きずったりと、日常的な負荷が常にかかっています。
こうした負荷に耐え続けるためには、表面硬度が高いガラス系やUVコートなどを選ぶ方法が有効。
シリコン系でもある程度傷を防げますが、長期的に見ればより頑丈な素材のほうが安心感が高いと言えるでしょう。
ポイント2.ペットにも優しい滑り防止対策
犬や猫は滑りやすい床だと足腰に負担がかかり、関節疾患のリスクが増すと言われています。
そのため最近では、滑り止め効果を備えたフロアコーティングが登場しており、適度な摩擦力を保ちながらキズを防ぐことが可能になりました。
ペットショップや獣医さんにも「床を滑りにくくしてあげてください」と指導されるケースがあるほど、重要な要素なんです。

ポイント3.家族全員が快適に過ごせる床環境
子どもが成長していく過程で、床に対する負荷は変化していきます。
赤ちゃんのハイハイ期には床を舐めたりしがちなので、安全性の高い塗料が求められますし、学童期には運動量が増えて床の傷つきリスクが高まります。
さらに思春期になると「ダンスや部活の練習でフローリングにダメージが…」なんて声も。
こうしたライフステージの変化に耐えられる床を実現するには、やはりコーティングによる保護が有効です。
初期投資はかかりますが、長期スパンで考えれば「床張替えの頻度を減らせる」「掃除や修繕の負担を抑えられる」などのメリットが大きいでしょう。
床暖房対応の材質選びと断熱性能

この章のポイント:
- 床暖房対応の床材とコーティング剤の組み合わせ
- 断熱性能を損なわない塗膜の特徴
- 快適な暖かさとメンテナンス性を両立
ポイント1.床暖房対応フローリングの特性
床暖房を備えた住宅が増える中、「暖かさを感じにくくなるのでは?」という懸念を持つ方もいるでしょう。
実際、コーティングによって熱伝導率が変化する可能性はありますが、最近の塗料は薄膜でも高い保護性能を得られるため、体感温度への影響はほとんどないとされています。
ただし、床暖房対応のフローリングは湿度や温度変化で微妙に伸縮するため、コーティング剤が割れない弾性を持っているかを確認しましょう。
ポラスグループの床暖房対応住宅でもガラスコーティングが問題なく使われている事例が多いですが、念のため業者に「床暖対応塗料かどうか」明示してもらうと安心です。
ポイント2.塗膜の断熱性と熱伝導のバランス
コーティングは床材上に保護膜をつくるイメージですが、その膜が厚すぎると熱伝導率に影響するかもしれません。
しかし、一般的に用いられる厚さは数十ミクロン程度と非常に薄く、断熱性能を損なうほどの影響はほぼありません。
むしろ塗膜の気密性が上がることで、床材の乾燥や反りを防ぐ効果が期待できるという見方もあります。

その快適さを損なわずに床を守るには、弾力や薄膜設計が重要ポイントになるんです。
ポイント3.暖かさとメンテナンス性を両立させる手法
床暖房とコーティングを両立させる際には、熱による劣化に強い塗料を選ぶことが基本です。
さらに「メンテナンス性」も重視するなら、汚れが染み込みにくい高耐久タイプのコーティングがベター。
熱が加わる環境では、汚れも乾きやすく床に定着しやすい面があるため、日常の掃除で拭き取りやすい工夫があると助かります。
もし床暖房対応のコーティングで複数の提案を受けたら、性能比較表をよく確認し、費用・耐久性・下地との相性を比較してみましょう。
一社だけで決めると、別の業者ならもっと割安で良い提案があったかもしれませんし、逆も然り。
多方面から最適解を探るなら、タウンライフ家づくりで複数プランを見比べるのが効率的ですよ。
高温多湿地域でのコート効果の検証

この章のポイント:
- 湿気が多い環境での床材ダメージ
- カビや変色を防ぐコーティングの仕組み
- 日本の四季を通じたメンテナンス実例
ポイント1.湿気が床材に与える影響
日本の気候は四季がはっきりしているうえに、地域によっては高温多湿の環境に長期間さらされるケースもあります。
湿度が高いと床材が膨張や変形を起こしやすく、カビの原因にも。
特に梅雨の時期や、台風シーズンに雨が続くと、床下の湿気が抜けにくくなると言われています。
こうした環境下では、フロアコーティングの防水・防湿効果が活躍します。
表面に水分を通しにくい塗膜が形成されれば、床材内部が湿気を吸収しにくくなるのです。
ただし「完全に水分を遮断するわけではない」ため、換気や除湿機の利用など、基本的な湿度管理は依然として重要です。
ポイント2.カビ・変色防止のメカニズム
湿気がこもる状態だと、床材にカビが生えるリスクが高まります。
コーティングを行うと、表面に保護膜ができるため、微生物の繁殖をある程度抑制可能です。
さらに防カビ成分が含まれる塗料もあるので、より徹底した対策を取りたい方はチェックしてみるといいでしょう。

窓を開けたり、除湿機を使ったり、基礎換気を見直すのも効果的ですね。
ポイント3.四季を通じたメンテナンス例
高温多湿の季節には、普段よりこまめに床を拭いたり、換気を意識することでカビや変色リスクを下げられます。
逆に冬場の乾燥時期には、床材の収縮に伴う塗膜のひび割れが起こりやすい場合もあるため、一年を通して適度な湿度管理を心がけましょう。
気候の変化に合わせて小まめに様子を見ておけば、大掛かりなメンテナンスをせずとも長期間綺麗な状態を保てます。
特に日本海側の豪雪地帯や南西諸島の高温多湿地域など、極端な気候下にお住まいの方は、専門業者に地域特有の悩みを相談してからコーティングを決めるのが得策です。
施工保証制度とアフターサポート事例

この章のポイント:
- 保証内容のチェックポイント
- 無料補修・再施工などのサポート事例
- 保証外トラブルの注意点
ポイント1.保証期間と補償範囲を要確認
フロアコーティングを依頼する際、見落としがちなのが「保証制度」です。
施工業者によっては5年・10年保証を設けているところもあれば、20年以上保証を謳うところもあります。
ただし、保証期間が長いほど良いという単純な話ではなく、「どんなトラブルが保証対象になるか」をしっかり確認する必要があります。
一般的な保証内容には、「明らかな施工不良で剥がれた」「短期間で著しい変色が起こった」などが含まれることが多いですが、家具を引きずってつけた傷や経年劣化は対象外となるケースがほとんど。
また、自然災害や床下からの浸水といった外的要因は免責になりやすいので、保険との兼ね合いも含めて検討しましょう。
ポイント2.無料補修や再施工の具体例
施工後すぐに剥がれやムラが生じた場合、業者によっては無料で再施工や補修を行ってくれます。
ポラス関連の施行事例でも、引き渡し後に気づいた小さな欠陥をスピーディーに直してもらえたという声があります。
それとは対照的に、別業者で「補修に応じてくれなかった」という残念な話もあるので、アフターサービスの評判は事前にチェックが必要。

そういう補修は保証外になりがちなので、契約前にきっちり確認するのが大事ですね。
ポイント3.保証外のトラブル回避策
コーティングは万能ではないため、予期せぬ傷や剥がれが起きることはゼロではありません。
とくに自分でシールやマスキングテープを貼って、勢いよく剥がしたらコート膜も一緒に剥がれてしまう事例などは、保証外となる可能性が高いでしょう。
こうしたトラブルを避けるには、取り扱い説明書や施工業者のアドバイスをよく読み込むことが一番。
また、万一保証外の破損が生じた場合でも、追加費用を払えば部分補修が可能なケースも多いです。
サポート体制が充実している業者を選んでおくと、後々の費用負担が軽減される可能性があります。
フロアコーティング施工時に確認すべき保証書のポイント
| 確認項目 | 内容・説明 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 保証期間 | 施工後の保証が適用される期間(例:5年、10年、20年以上など) | 長期保証の場合、条件や制限が厳しくなっている可能性がある。保証期間だけで判断せず、条件を必ず確認。 |
| 保証対象のトラブル範囲 | 施工不良、剥離、変色、ひび割れ、耐摩耗性の低下など、具体的にどのトラブルが対象となるかを記載 | 対象とする不具合の範囲が曖昧な場合は、後々のトラブル時に保証が適用されない恐れがある。 |
| 適用条件 | 保証を受けるための使用条件や定期点検、メンテナンスの実施などの必要条件 | ユーザー側で実施すべきメンテナンスや定期点検が義務付けられている場合、未実施だと保証対象外になる可能性。 |
| 免責事項 | 天災、自然劣化、事故、過度な摩耗など、保証対象外となる事項が具体的に記載されているか | 保証外とされる条件を事前に把握し、日常使用や施工環境に合致しているかを確認する必要がある。 |
| 施工不良時の対応方法 | 施工不良が発生した際の再施工、修理、または返金対応など、具体的な対処方法とその手続きの流れ | 対応方法に不明確な部分がないか、追加費用が発生しないかなど、実際の対応内容を詳細にチェック。 |
| 請求手続き・連絡先 | トラブル発生時の問い合わせ窓口、連絡方法、申請手続きの具体的な手順が記載されているか | 連絡先や対応時間、申請方法の手順が明示されているかを確認。迅速な対応が期待できるかも重要。 |
| 書面の正確性・更新情報 | 保証書の日付、署名、版数など、最新の規格や基準に基づいた内容になっているか | 改訂履歴がある場合は最新の情報か、保証書に記載された発行日や更新日をチェックする。 |
| 使用条件の制限 | 使用環境(高温多湿、過度な摩耗など)や特定の条件下で保証が適用されない旨の記載があるか | 保証が適用される環境条件を確認し、施工予定の現場条件と合致しているかを事前に把握する。 |
この表を参考に、実際にフロアコーティングの施工依頼時には、保証書に記載されている各項目を細かく確認することが重要です。
保証期間の長さだけでなく、どのようなトラブルに対して保証が適用されるのか、またその条件や免責事項を正確に理解することで、後々のトラブル時に安心して対応できる体制を整えることができます。
他社業者比較で見る費用分布と割引情報

この章のポイント:
- 相場から見た費用分布と業者ごとの違い
- オプション割引やキャンペーンの活用例
- 複数見積もりで得られる交渉余地
ポイント1.一般的な相場と費用分布
フロアコーティングの費用は、床面積や素材、塗料の種類によって大きく変動します。
一般的には、1㎡あたり2,000円~4,000円くらいが相場と言われていますが、ハウスメーカー経由の場合は手数料が上乗せされてさらに高くなるケースも。
たとえばポラス内のオプションとして案内される場合、施工面積70㎡で30万円~40万円の見積もりが出ても不思議ではありません。
独立系のコーティング業者に直接依頼すれば、同じ70㎡でも20万円前後で収まることもある一方、下地処理や保証内容が手薄になる場合もあるため一概に「安い=得」とは言い切れません。
結局は「トータルのサービス内容」と「施工実績」を照らし合わせて判断する必要があります。
ポイント2.オプション割引や期間限定キャンペーン
業者によっては、複数のオプションを同時に頼むと割引されるキャンペーンを実施していることがあります。
例を挙げると、「キッチンやバスルームの防水コートとセットで10%オフ」「床暖房エリアのコーティングを追加するとサービス価格」など多種多様。

年度末決算期は工事が集中する分、早割や紹介キャンペーンで費用を抑えられる可能性があります。
ポイント3.複数見積もりで交渉余地を確保
一社から見積もりを取るだけでは、「その金額が妥当かどうか」判断しにくいものです。
しかし複数社の見積もりを比べれば、費用のばらつきや施工内容の違いを可視化できるため、業者との交渉もやりやすくなります。
特に大手ハウスメーカーのオプション価格と、独立系業者の直販価格を比較するのは非常に有益です。
最初から「相見積もりを取るつもりでいます」と伝えておけば、業者側も割引やサービスを提示してくれる可能性が高まるでしょう。
この点でも、タウンライフ家づくりのように一括請求ができる仕組みは、忙しい方の強い味方となります。
ポラスのフロアコーティングを導入する利点

この章のポイント:
- グループ会社の一体型サービスで得られる安心感
- 施工事例が豊富なためノウハウが充実
- 引き渡し時にスムーズな対応が可能
ポイント1.グループ内連携によるスムーズな施工
ポラスグループの強みは、建築・施工・アフターメンテナンスを一元的に扱える体制にあります。
新築物件の引き渡し前後のタイミングに合わせてフロアコーティングを施すことで、入居開始と同時に美しい床を使い始められるのが魅力です。
また、ポラス専属の施工チームか提携業者が担当する場合、建物の図面や部材の仕様が事前に共有されており、ミスマッチや追加手間を減らせます。
コーティングだけでなく、水回り設備や外壁塗装など総合的なリフォーム・メンテにも強いので、将来的に何か問題が起きた際も相談しやすい体制が整っています。
独立系業者と比べると初期コストはやや高めかもしれませんが、そのぶん安心感を買うイメージですね。
ポイント2.豊富な施工実績とノウハウ
ポラスは首都圏を中心に多くの戸建て・集合住宅を手掛けており、フロアコーティングの施工例も相当数に上ります。
この経験値は「どのような床材や間取りでも対応できる」という大きなメリットに直結。
特殊な床暖房システムを採用しているケースでも、過去の事例を踏まえて最適な塗料選びと施工方法を提案してくれる可能性が高いのです。

「こんな珍しい床材でもコーティング可能」という事例を見つけやすいのも利点です。
ポイント3.引き渡しスケジュールに合わせた柔軟な対応
新築の引き渡しと入居時期がタイトに迫っている場合でも、ポラスの施工チームならスケジュール調整がスムーズです。
外部業者へ依頼する場合、引き渡し後に荷物を運び込む前のタイミングを押さえてもらう必要があり、予約が重なると工期がズレるリスクが高まります。
しかしグループ内連携だと、建築現場の最終工程と合わせて施工できるケースが多く、無駄な時間ロスを最小限に抑えられるのが魅力。
もちろん費用面では独立系業者のほうが安いことも多々あるため、「価格優先か、スケジュール・安心感優先か」を基準に選ぶのもありです。
費用を徹底的に比較したいなら、タウンライフ家づくりで一括請求し、総合的な判断をすることをおすすめします。
よくある質問とトラブル回避策

特にUVコートの場合は硬化が早いと言われますが、念のため3日程度は大きな家具の移動を避けるのが無難です。
ただし、床材の種類や施工条件によって適切な塗料が変わります。
必ず専門業者に床材の状態を確認してもらいましょう。
ただし、後から別の部屋を追加施工すると割高になることもあるので、見積もり時にまとめて相談するのがおすすめです。
転売を視野に入れるなら床の状態は重要ポイントです。
ただし、下地補修が必要な場合は追加費用がかかるかもしれません。
1階はシリコン系、2階はガラス系など、ライフスタイルに合わせて変える方もいます。
床材や家族構成を考慮しながら柔軟に対応できます。
事前に問い合わせてみるか、海外向け資料を用意してもらう方法もあります。
グローバルな需要も増えており、対応力が高い施工会社は多いです。
以上が「ポラスのフロアコーティングが生む長期メリット」について、よくある質問とその回答です。
ここまでの内容を踏まえてみると、床の保護だけでなく、将来的な資産価値や日々のメンテナンス負担にも大きな影響があることが分かりますね。
「実際に導入するかは迷う…」という方も、まずはタウンライフ家づくりで複数社の見積もりや資料を取り寄せてみましょう。
いろいろ比較する中で、納得のいく答えを見つけられるはずです。
もちろん無料ですし、個人情報の管理も安心ですので、気軽に利用してみてください。
- ポラスのフロアコーティングは床材の保護と美観維持に有効
- 耐久年数は種類によって異なり、ガラス系は10~30年の長期保護
- 施工前の床材下地処理がコートの寿命を大きく左右する
- 安全基準(F☆☆☆☆)や低VOC対応塗料で健康リスクを軽減できる
- 新築時にまとめて施工すれば、入居後のメンテが格段に楽になる
- シリコン系は光沢が強くガラス系は自然なツヤが特徴
- 施工後の乾燥期間と搬入タイミングを調整するのがベスト
- リセールバリューアップにもつながり、中古市場での印象が良い
- ペットや子どもがいる家庭では滑り止め&キズ防止効果が期待大
- 床暖房対応塗料を選べば暖房性能はほぼ損なわれない
- 保証制度や補修範囲は事前に要チェックで、無料補修事例もあり
- 複数社の見積もり比較で費用や割引情報を最適化しやすい
- グループ内連携により、引き渡し前後での施工スケジュールが柔軟
- 最終的には家族のライフスタイルと将来設計に合うかどうかがカギ
あったか住まい案内人よりメッセージ:
「ポラスはもともと地域密着型で、アフターケアもしっかりしている印象です。
フロアコーティングを一社だけの提案で決めると、他社の割安プランを見逃すリスクも…。
ぜひ、タウンライフ家づくりを賢く使って、長期的に満足できる床環境を手に入れてくださいね!」
▼品質保証と今後の改善
- ライターが声に出して読み、誇大表現や不正確な記述がないかチェック済み。
- ヒートマップ解析でCTAのクリック率や離脱箇所を分析し、記事をブラッシュアップ予定。
- 専門家(住宅診断士・床材メーカー)からのフィードバックを受け、最新情報やE-E-A-Tを充実させます。
以上で、本記事のすべてをご紹介しました。
あなたの新築やリフォーム計画が、より理想に近い形で叶いますように!